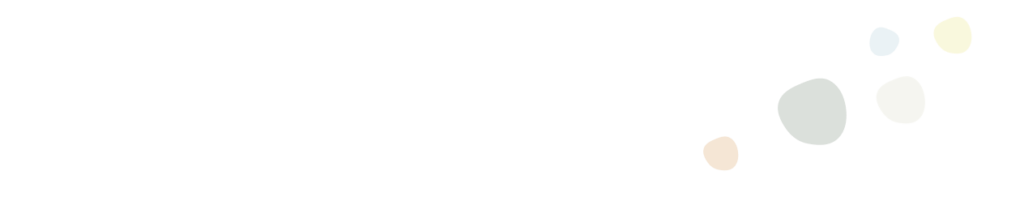あそび場づくり事業
PLAY FIELD事業では乳幼児から小学生の「未来を創る力」が育つ、あそび場事業運営の仕組みづくりに取り組んでいます。
PLAYFIELD(あそび場)の特長
みんなでつくる!
PLAYFIELD(=あそび場)の遊びは、子どもの「やりたい!」から始まり、「いいこと思いついた!」で変化していく、子どもたちがつくるものです。「あそび場」にある遊具や備品の作成、イベントの準備や進行等は、保護者や地域の方々にもご協力頂きながら、子どもと大人がみんなでつくることを楽しんでいます。そして「あそび場」の運営は、自治体の運営資金等のサポート、寄付、近隣施設との連携、専門家の知見等、様々な属性の方の想いとお力が集まることで実現しています。

子どもの「遊ぶ力」が育つ
PLAYFIELD(=あそび場)にある道具は、どこの家庭にもあるような物が多く、廃材やリサイクル品も集めています。理由は、子どもが自由自在にアレンジできるからです。また、枝、石、葉、土、水、火、生き物等の自然や、土地の起伏や登れる木等のフィールド環境も、使えるものは何でも遊びに活用します。働きかけ次第で様相が変わる自然は、子どもたちの探求心をくすぐり、「あ、いいこと思いついた!」が次から次に飛び出す魅力的な遊び素材です。
「あそび場」が大切にしているのは、子どもたちが身近にある素材や環境を使って、どこででも!遊べる「遊ぶ力」が育つことです。

「子ども主体」のノンプログラム
PLAYTIELD(=あそび場)には、遊びのプログラムも大人の指導もありません。遊び方のルールは、状況により子どもが変えていきます。「何をして?誰と?どうやって?遊ぶかを決めるのは子どもだ」という、冒険遊び場マインドの「自分の責任で自由に遊ぶ」を体現しています。ココで言う責任とは、判断が子どもに任されるresponsibility(対応責任)です。例えば転んだ時、泣く?誰か呼ぶ?一人で立ち上がる?を決めるのは、子どもだということです。
ノンプログラムのあそびの”主体” は子どもです。自分で考えて自分でやった満足感や達成感の積み重ねは、多少のことでは揺らがない”自己肯定感”の土台になります。

外遊びにこだわる!
外で遊んでいると、自然や異年齢・異世代の人と関る機会が増えます。知らないこと、予想できないこと、自分とは違う異質さへの許容力が広がります。予定調和のない雑多な状況だからこそ育つのは、柔軟な発想やヒラメキ力です。また、暑い日も寒い日も外で遊んでいれば、自律神経の機能が高まります。暑さ寒さや感染症への適応力も、しなやかな身のこなしができる身体力も育ちます。
AIの登場やSDGSを掲げる程の環境変化が起きるこれからの社会で求められる力に、多様性への許容力、状況への柔軟な対応力、そして、地球規模の環境変化に適応するしなやかな身体力があるとしたら、外遊びは、その全てが育ちます。